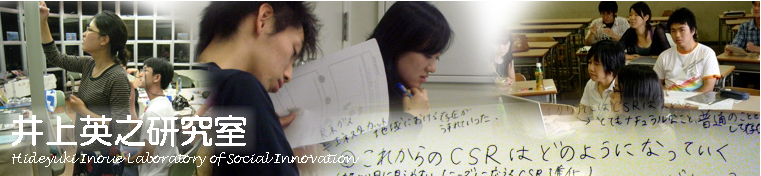「12/3ミッションマネジメント」
PRESENTED BY ネセサリー
●目次
1. Intro
2. 既存の戦略論 〜マイケル・E・ポーターから学ぶ〜
3. 新しい戦略から、ミッションマネジメントが見えてくる!
4. 具体例を見て、ポイントを整理しよう!
5. Outro
● イントロ By りかこ
・ Golden Eggsのアニメ
Golden EggsのHP(http://www.theworldofgoldeneggs.com/)
—Massage:「監督のネセサリー体操によって、最後には、同じものをみつめていた。」
・ ミッションって何?
—北極星=ミッション
—北極星を構成するもの
)ビジョン:自分たちの目指すべき姿
)ミッション:ビジョンを実現するためにどういった方針で、どういった目標でビジョンを達成していくのか
)バリュー:組織(個人)の性格、価値観
—具体的な行動:北極星に向かう矢印
Massage from Nessarary:
今回の授業は、マイプロに活かしてもらいたい。
・ みんなの北極星、ビジョン、ミッション、バリューとは何ですか?
—はせの例:「ビッグイシュー日本」の借り物競走をコーディネート
)ビジョン:ビッグイシュー日本をホームレスが自立しやすい組織にすること
)ミッション:
・企業や個人の力(ビッグイシュー日本単独ではもっていないリソース)を渉 外担当として集める。
・渉外担当として実行したプロジェクトについての「ホウレンソウ」をしっかりと行う。
・ビッグイシュー日本のスタッフさんに、自身の強みを自覚させ、借り物競争ができることを知ってもらう。
)バリュー:借りるだけではなく相手にとってのwinを示すことで長期的関係に持っていくこと。
—あーちゃんの例:「大学生のエリート意識に火をつけろ!プロジェク ト〜SIFE Japan建て直し計画〜
)ビジョン:日本、そして世界の将来を担う人材が育つ場所であることを目指します。
)ミッション:
・SIFE Japanは、学生にとって大学で学んだことを活かせるさらなる学びの場となります。
・SIFE Japanは、世界の学生と日本の学生をつなげ、世界のレベルを体感できる場となります。
・SIFE Japanは、日本の学生が世界に接点を持つためのサポートを行います
・SIFE Japanは、「育てる視点」を持った企業や社会人と学生をつなげ、よきメンターを提供します。
)バリュー:SIFE Japanは、大学生は社会から多くの投資を受けた未来を担うエリートであると考えます。
りかこ:
なぜマイプロを整理するか?
今の現時点を知って、授業する前とした後でビフアーアフターを比較してみる。
・ ミッションマネジメントとは?
➢ たくさんの議論や論点があるが、今回は、ビジネスの「経営戦略」の側面からマネジメントを学んでみます。
いのさん:
アンダーセンが定義したのは、NPOとかとは異なる。
ノンプロフィットの場合、ミッションに「社会」が入ってくる。
具体的な行動から、事業化していくことがミッションから落ちて行くミッションマネジメント。
企業は企業が主語だから、ビジョンに「私=企業」が入ってくる。
りかこ:
今回はビジネスだけど、ノンプロフィットバージョンもあると思う。今回は、ビジネス側から学んでみよう。
バードさん:
ワードのなかで、ビジョンとミッションの順番が違うのは意図している?
つじけん:
はい、意図しています。
いのさん:
ミッションの下に、目標とか書いてはいけない。オブジェクトだから。
ワシントンDCでは、
各ディパートメントがあって、最初ミッションからはいる。こういう地域を守る!というミッションがあって、そのあとに、ビジョンに入る。
目的によって、使いわけている。
ビジョンを描くのは、市長とかで、そのビジョンに基づいて、市民の人に何が大切かプライオリティをつけてもらって、そのあとにストラテジーをつくってもらう。上から下にいくやり方。
● 既存の戦略論 〜マイケル・E・ポーターから学ぶ〜 Byナンシー
・ なぜマイケルを学ぶのか?
—戦略の「主流」を学ぶため
・ マイケルとは?
「競争の戦略」を発表、世界に新風を巻き起こした人。
・ マイケルの言う戦略とは?
戦略とは、「他社と異なる活動を伴った、独自性のある価値あるポジショニングを造り出すこと」である。
これを“戦略的ポジショニング”といい、これを重視している
・ マイケルの競争戦略の理論とは?
産業の実証的研究と豊富なデータの分析から、
産業内の競争を支配する5つの要因を明らかにし、
自社の有利に働き、競争を支配ひうるポジショニングを乱すことが
競争戦略の要諦である。
「5つの競争要因」
1 新規参入の脅威
2 サプライヤーの交渉力
3 顧客の交渉力
4 代替製品や代替サービスの脅威
5 産業内のポジショニング争い
・ 戦略の策定
競争を左右している要因と、根本にある原因を評価できたら、
戦略担当者は自社の長所と短所を特定し、そこから行動プランをたてる
1)自社の能力を最大限いかせるようなポジショニング
例)ドクターペッパー
コーラーと同じものを売ってもしょうがいない。
コカコーラとは異なるデザイン
2)競争要因のバランスを変え、自社のポジショニングを改善する
3)業界の変化を利用する
・ 注目すべき点
戦略担当者は行動プランをたてる
つまり、戦略は、戦略プランナーによってつくられる。
・ しかし!!論理分析的戦略論の限界
ヘンリーミーツバーグの主張:
「分析することで、総合かが図られる。したがい、戦略プランニングとは戦略を創造することである。」
・ おまけに、ドラッガーも似たようなことを・・・ BY まりなっちょ
イノベーションは、その本質からし、分権的、暫定的、自律的、具体的、ミクロ経済的である。そして、小さなもの、暫定的なもの、柔軟なものとしてスタート。
まりなっちょ:
ユヌスは、一回やってみて、事業化してみた。という事例を思い出して、腑に落ちた。
いのさん:
働くようになったら感じると思います。
変化が早いITベンチャーでは使えない。
ミーツバークのような直感的な考え方が支持を集めてる。
● 新しい戦略から、ミッションマネジメントが見えてくる! BY たっくん
・ ミンツバークって誰?
純理論的な経営理論(マイケル)を批判。
ただ、マイケルとミンツバークは対立してるものではない。
・ 本来の戦略=ミッションマネジメント?
—「現場」の捉え方
—「学習」の意味すること
→この辺からミッションマネジメントの重要な側面が見そう。
たっくん:
井上研では、専門家にみえるけど、そうではない。現場にもっともっといきたい。
・ 戦略クラフティングとは 〜実際の戦略はこうして生まれている〜
「純粋なプランニング戦略と純粋な創発戦略は、一本の線上に両極にあり、
ほとんどの戦略はこの線上の中間に落ち着くことになる。」
・ 実効性の高い戦略 〜「学習」がクラフティングを可能にする〜
・ アンブレラ戦略 〜全員で戦略を作っていく〜
プランニングだけでなく、創発のプロセスも含んでいる。加えて、戦略が途中で発展するように意図的に管理している点で,計画的に創発を促すと言える。
・ 戦略思考 〜戦略はいつでもどこでも生み出せる〜
「誰でも持ち得る」もの。
・ 野中郁次郎って誰?
日本では数少ない経営学者
・ 日本的経営
「暗黙知(べったり)の経営」ではなかった。暗黙知と形式知の相互。
・ 境界知とは?
—形式知:文章化、によって説明、表現できる知識のこと例)マニュアル
—暗黙知:経験や勘に基づく知識のことで、言葉などで表現が難しい。例)こつ、勘
—境界知:違和感を感じることによって境界を見いだす知
・ 賢慮?!(アリストテレスの考えに似てる??)
—エピステーメー:科学的(分析的)な知
—テクネー:現場が持つ経験則
—フロネシス:実践で活きる 人間力
いのさん:
テニス言葉で教わるときが知。でもうってみないとわからない、それが現場。
ただ、試合に勝とうと思ったとき、その場の状況に合わせてやらないとだめ。
・ ぷちまとめ1 〜郁次郎とミンツが出会います〜
1)ミンツバークのいう「形成していくプロセス」
=>多かれ少なかれ「分析、プラン」が必要
=>求められるのは「形式知/エプステーメー」
2)ミンツバークのいう「実行するプロセス」
=>求められるのは「暗黙知/テクネー」
3)ミンツバークのいう「学習」
・ 「学習」とは何か? 〜現場をインプットの場を捉える〜
・ 失敗のプロセス
—ミッション・ビジョン→目標→仕組み→学習→現場 これでは失敗
・ 成功のプロセス
—ミッション←目標←仕組む←学習←現場
いのさん:
共感して集まって、コミュニティが出来上がってるときは良いけど、だんだん組織が成長していくと(仕組み化すると)、ちゃんとしなきゃ!と思うようになり、決めた事だからちゃんとしよう!という風になって、現場とニーズがあわなくても決めたことを先にやるようになる。
だんだん、空気をよむようになって、「個人的な意見」がなくなる。しかし!!その個人の意見を吸い出すことがどれだけ大切なことか。
・ まとめ
戦略クラフティングの必要性は、様々な視点から確認できる。
特に、「現場」と「学習」という二つのキーワードの関係性。
いのさん(アドバイス):
抽象度の高い話は、1つ2つ事例を用いた方がいいよ。
● 具体例を見て、ポイントを整理しよう! By つじけん
1)大前提:星は動く。動く☆を常にキャッチせよ
ミッションやビジョンは時間の経過とともにその内容が見直される。
事例)リクルート byまりなっちょ
現状維持とは、ものすごいスピードで世の中から遅れること。
・ 外飯/外酒:周囲の人に聞く
2)常に同じ北極星を判断材料に!
どの意思決定の場面でも、北極星に基づく。
上の人はビジョンを見つめていても、下の人は見つめていない場合もある。
一見違う北極星
「幹部の北極星」 =社会をよくする
「平社員の北極星」=お金をもうけろ!
しかし
「幹部の北極星」 =社会をよくする
「平社員の北極星」=(社会をよくするためには、お金がかかる。)お金をもうけろ!
3)動く北極星に注意せよ!
固定された北極星は原点回帰するのではなく、動き回る北極星を判断材料に
する。
事例)サウスウエスト航空 byはるぴ、ナンシー
はるぴ:
北極星に照らし合わせる。
従業員も、創業者より上手に伝えられるほど浸透し、理解されているので、従業員は経営会議など開く必要なく、自分の判断で行動できる。
ナンシー:
「目標がしっかりしていれば、どんな複雑なアイディアが持ち込まれようと、その目標に照らして、これは、私のビジョンにそった素晴らしいアイディアなのか?そうでないなら邪魔しないでくれと問い直すことができる。」と社長は言う。
いのさん:
パンツをはかせちゃうことで、言葉では伝えないけど、組織をデザインしている。
4)上から下からのマネジメント~どのレイヤーの社員にも北極星を伝えて理解させる~
・ 上からのマネジメント
—実際の企業経営の中で充分に発揮されるためには、上からのミッションの展開を実施することが重要。
・ 下からのマネジメント
—アンブレラ戦略:プランニングだけでなく、創発のプロセスも含んでいる。
➢
事例)リッツカールトン byじゃすみん、りかこ
じゃすみん:
下からは、「多様性に価値を見出し、生活の質を高め、従業印の夢を実現」するという方針を掲げているのが印象的。
いのさん:
「クレド」というのは、価値観を言語化しただけでなく、仕組みとなっているのがすごい。自分自身がリッツカールトンを体現することができる。
じゃすみん:
クレド以外にも、他にも文章化した仕組みがある。
いのさん:
最初のグラミンバンクを思い出す。
りかこ:
リッツカールトンは、上から下からの良い事例
・ 上からの事例
➢ リッツカールトンにとってスタッフは財産『エンプレイー・プロミス』
・ 下からの事例
➢ 現場から聞き出す『ストーリー・オブ・エクセレンス』
5)全てのステークホルダーに共感を〜北極星は社員が共感するだけでなく、全てのステークホルダーに〜
勝手に作ってしまったビジョンではだめで、他の人も共感を得ることが大事。
事例)HONDA byもっちー、つじけん
もっちー:
ワイガヤとよばれる上下関係・過去の資料をいっさい蒸しした会議を実施している。
つじけん:
基本理念①人間尊重:立場によって差別しない!!
基本理念②3つ(買う、売る、創る)の喜び:顧客の喜びを第一に考える。
つじけんのおじは、最近は大企業病になってるのではないか?と言っている。
大企業病:大量生産、売り上げ重視しているようになってしまうこと
まりなっちょ:
「感じるマネジメント」をよんだ。どう共感を得ていくか、ということが書いてあるので、是非読んでみて下さい。
● OUTRO Byりかこ
・ REVIWE
—マイケルでは限界→ミンツバーク
—現場と学習について「美徳の経営」「学習する組織」からもみました。
—ミッションマネジメントの具体例もみました。
—次回は、マイプロ発表も行います。
越くん:
フローレンスでインターンしていました。
前に比べ、授業内容が難しいことしているなーという感覚。
バードさん:
ハーバードビジネスレビューを読み始めています。
すこっちさん:
NPOでリーダーをしていないとあまり実感がわかないのかなと思いました。
これを以前の井上研で学んでる人は、復習も大切です。
話のフレームはあんまり変わってないなという印象。
みっちー:
イルミネーション湘南台という場所で、いやっとするほど考えてきたので、なるほどなーという感覚でした。
おくだめさん:
よくまとまっていて、すごいなーと思いました。
経営戦略論でも、まとめたら利益追求をゴールとしている人と、ミッションをゴールとしている人の二パターンがあるなという感じでした。